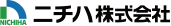2025.11.07
上棟式・棟上げとは何をするもの? 建前とたちまいとは? 大工さんへのお礼としてご祝儀や手土産は必要?
建築には、いくつかの伝統的な祭式があります。中でも地鎮祭・上棟式・竣工式は建築の三大祭式と呼ばれ、工事の無事やその土地・建物における安全・安心な暮らしを祈るための儀式として大切にされています。
これらは戸建て住宅などの小規模な建物を建築する際にも行うことがあるため、家を建てる時に実施すべきか悩む方もいるのではないでしょうか。この記事では、そんな三大祭式のひとつである「上棟式」について記述します。戸建て住宅で実施されることの多い簡略的な上棟式に加え、ご祝儀や手土産のマナー、費用の目安などもわかりやすく解説します。
注文住宅を建てるまでの流れについての詳細は下記の記事をご覧ください。
⇒「家を建てるまでの流れが知りたい! 年収や頭金はどれぐらい必要? 注文住宅の基礎知識」
建築の三大祭式「地鎮祭」「上棟式」「竣工式」

建築の三大祭式である地鎮祭・上棟式・竣工式を実施する時期と意味合いは下表の通りです。
| 時期 | 意味合い | |
|---|---|---|
| 地鎮祭 | 着工前 | 工事の無事な進行と土地・建物の末永い安全を祈願する |
| 上棟式 | 柱や梁の取り付け完了時 | それ以降の工事が安全に進むことを祈願する |
| 竣工式 | 竣工時 | 今後の安全・繁栄を祈願する |
これらはいずれも必ず実施しなければならない祭式ではなく、地域の風習などを考慮して施主が実施を決められます。また、その規模も千差万別であり、近年では神主を呼ばない簡略的な祭式を行い、安全・繁栄を祈願するスタイルも増えています。
工事関係者と良好な関係を築くきっかけになることも、これらの祭式を催すメリットのひとつです。地元の工務店などに家づくりを依頼すると、アフターメンテナンスを含めた長い付き合いになります。関係者の顔を知っておけば不具合が生じた時も気軽に連絡できるでしょう。
地鎮祭についての詳細は下記の記事をご覧ください。
⇒「家づくりの際に行う地鎮祭とはどういうもの? 服装や初穂料など事前に知っておくべきこと」
棟上げとは

上棟式を語るうえで欠かせないのが「棟上げ」という工程です。棟上げは、家づくりの中でも特に象徴的な節目であり、職人の技が最も発揮される瞬間でもあります。「建前」「たちまい」といった呼び方の違いや、上棟式との関係を理解しておくと、家づくりの流れがより明確になります。
●「棟上げ」「建前」「たちまい」の意味と使い分け
上棟式と似た言葉に「棟上げ(むねあげ)」「建前(たてまえ)」「たちまい」があります。これらは、いずれも家の骨組みが完成し、屋根の一番高い部分である「棟木(むなぎ)」を取り付ける作業や、そのお祝いを指します。
正確には次のように使い分けられています。
・棟上げ、建前、たちまい:柱や梁、棟木を組み上げる作業そのもの
・上棟式:棟上げの後に行うお祝いの儀式
建前や棟上げは「工事の節目」、上棟式は「感謝と祈りの儀式」と考えるとわかりやすいでしょう。
●上棟式はいつ行う? 実施のタイミングと目的
上棟式は家の「骨組み」ができあがったタイミングで行います。具体的には柱・梁・棟木が組み上がり、家の形が見え始めた日に実施するのが一般的です。
上棟式を執り行う目的は次の2つです。
・建築の無事を祈願する
これから続く内装・仕上げ工事が安全に進むよう、神様や土地の神に祈ります。
・職人への感謝を伝える
上棟式は家づくりを支える大工や現場スタッフへの労いの気持ちを伝える行事でもあります。
また、家づくりの大切な節目を迎える行事であり、家族にとっても記念すべき機会となります。
上棟式を簡略化するケースが増加中

盛大な上棟式に代わり、費用や時間の負担を抑えた簡略的な上棟式を選ぶ家庭が増えています。神主を呼ばずに工務店や家族だけで行うなど、感謝の気持ちを大切にした柔軟なスタイルが主流になりつつあります。
●最近は「簡略的な上棟式」が主流に
近年では、昔ながらの大規模な上棟式に代わり、費用や時間の負担を抑えつつ、感謝の気持ちを伝える「簡略的な上棟式」を選ぶ人が増えています。
こうした変化の背景には「費用を抑えたい」「形式にこだわらず感謝を伝えたい」「仕事の都合で時間が取れない」といった理由があるものの、上棟式が持つ本来の目的である安全祈願と感謝の気持ちを重視するという傾向も見ることができます。
従来の上棟式は神主を招いて祈祷を行い、宴席を設けるのが一般的なスタイルでしたが、現在では工務店主導で行う30分〜1時間ほどの簡単な式が主流になりつつあります。神主を呼ばずに棟梁や現場監督が進行を務めることも多く、形式にとらわれることなく気持ちを伝えられる柔軟なスタイルとして定着しています。
●簡略的な上棟式の流れ
簡略的な上棟式は一般的に以下のような流れで行われますが、直会の儀(祭式後の会食)を行わないなど、さらに簡略化されることもあります。
・棟梁が幣串(へいぐし=魔よけの飾り)を設置する
・祭壇に御幣(ごへい)や神饌物(しんせんぶつ)などの捧げものを供える
・四方固めの儀を行う:施主と棟梁が四隅の柱に酒・塩・米・水などをまく
・二礼二拍手一礼でその先の工事が無事に進行するよう祈願する
・直会(なおらい)の儀を行う:施主が挨拶をして乾杯する
・手締めで式を締める
・施主から出席者にご祝儀や手土産などを渡す
●上棟式の依頼
簡略的な上棟式は、工務店などに主導してもらうため、上棟式を催す際は工務店に依頼します。神主を招く場合は、神主に依頼しましょう。戸建て住宅では基礎工事が完了するとあっという間に柱や梁の取り付けが完了します。相談が遅いと上棟式の実施が難しくなることも考えられるので、着工前にあらかじめ相談しておくと良いでしょう。

上棟式を準備する際は、以下の3つを進めましょう。
・人数の把握:家族・親族・工事関係者など
・日程の決定:六曜の大安・友引や十二直の建築吉日など
・物の準備:棟札・御幣・米・酒・弁当・菓子・飲み物・紙コップ・ご祝儀・手土産など
建築吉日は建築の祭式を行うのに良いとされる日です。六曜とは異なる歴注の「十二直」で、「建(たつ)・満(みつ)・平(たいら)・定(さだん)・成(なる)・開(ひらく)」が建築吉日とされています。
●上棟式の服装
伝統的な上棟式の服装はスーツなどのフォーマルなスタイルが一般的ですが、簡略的な上棟式ではカジュアルな服装で参加する人が増えています。関係者に失礼のないような清潔感のある服装が良いでしょう。
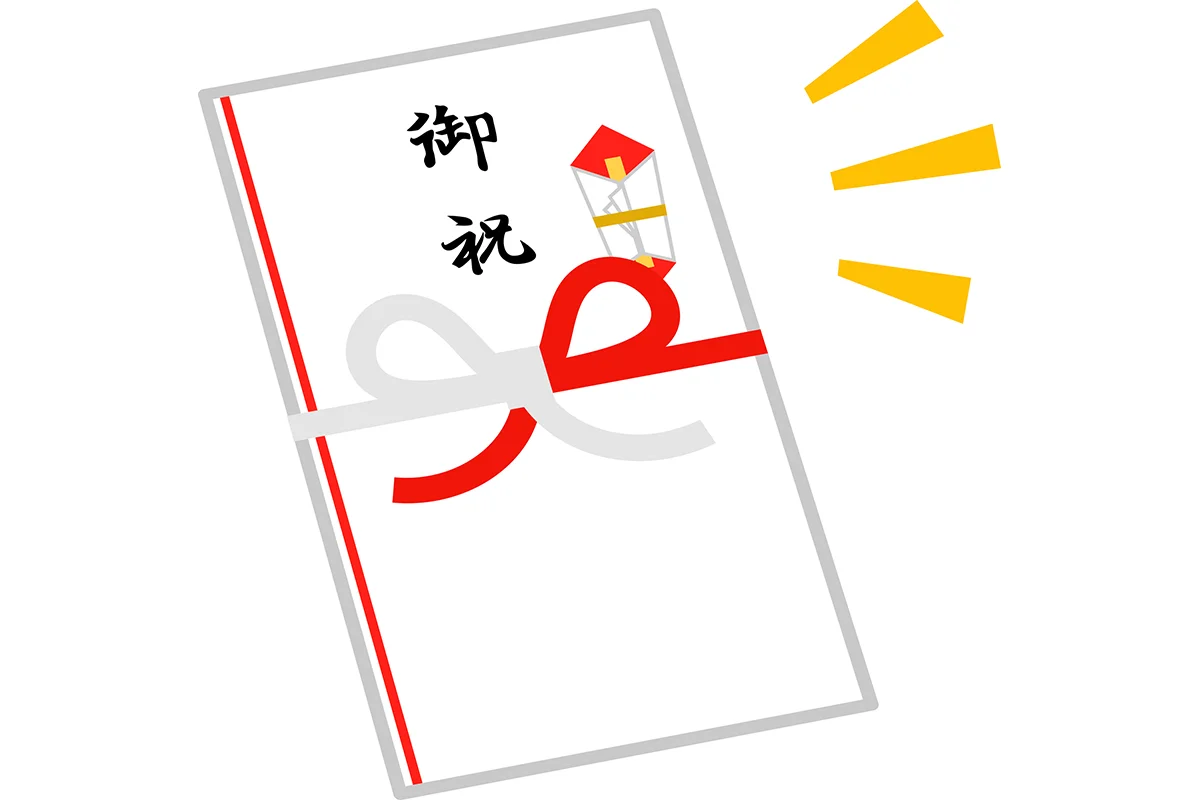
上棟式の費用は地域の慣習や規模、参加人数によって異なります。一般的には以下のような費用が必要とされていますが、金額はあくまで目安です。
棟梁:1〜3万円
大工・職人:3,000〜1万円/人
現場監督:1万円/人
お供え物:1万円程度
のし袋は紅白蝶結びの水引を使い、表書きは「上棟御祝」「御祝」が一般的です。金額は地域によって違いますが「日ごろの感謝を伝える気持ち」が何より大切です。
●上棟式の手土産マナー
手土産は職人さんたちに対する感謝の気持ちを込めて、実用的で気軽に受け取れる品を用意するのが好まれます。昔は「紅白まんじゅう」や「お餅まき」が一般的でしたが、現在は以下のような品が人気です。
・缶ビールやノンアルコール飲料の詰め合わせ
・お菓子・地元の銘菓
・タオルセットや日用品
・商品券
手土産の費用は1人あたり2,000〜3,000円前後が目安です。参加者が多い場合は全員に同じ品を配るよりも、棟梁や現場監督にだけ別途お礼を渡すなど、負担を調整する方法で工夫することもできます。
手土産を選ぶ際は持ち帰りやすく、分けやすい品を意識しましょう。お酒を振る舞うなら飲めない方への配慮としてノンアルコール飲料を用意すると丁寧です。現場の人数が多い場合は事前に工務店へ確認しておくとスムーズに配れます。
上棟式はやる? やらない? 施主が決める後悔しない選択

上棟式は必ず行わなければならないものではありません。「簡略的に行う」「職人に直接お礼を伝えるだけ」といった柔軟なスタイルも普及しています。
それでも、上棟式を行うことで得られるメリットは少なくありません。
・施主として家づくりの実感を得られる
・職人や施工会社と信頼関係を築ける
・家族にとっての記念になる
省略した場合も問題になることはありません。
予算やスケジュールの都合で行わない場合は、差し入れや感謝の言葉を伝えるだけでも十分です。
「形式にとらわれず、自分たちらしいやり方で感謝を伝える」ことこそが、後悔しない家づくりにつながります。