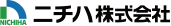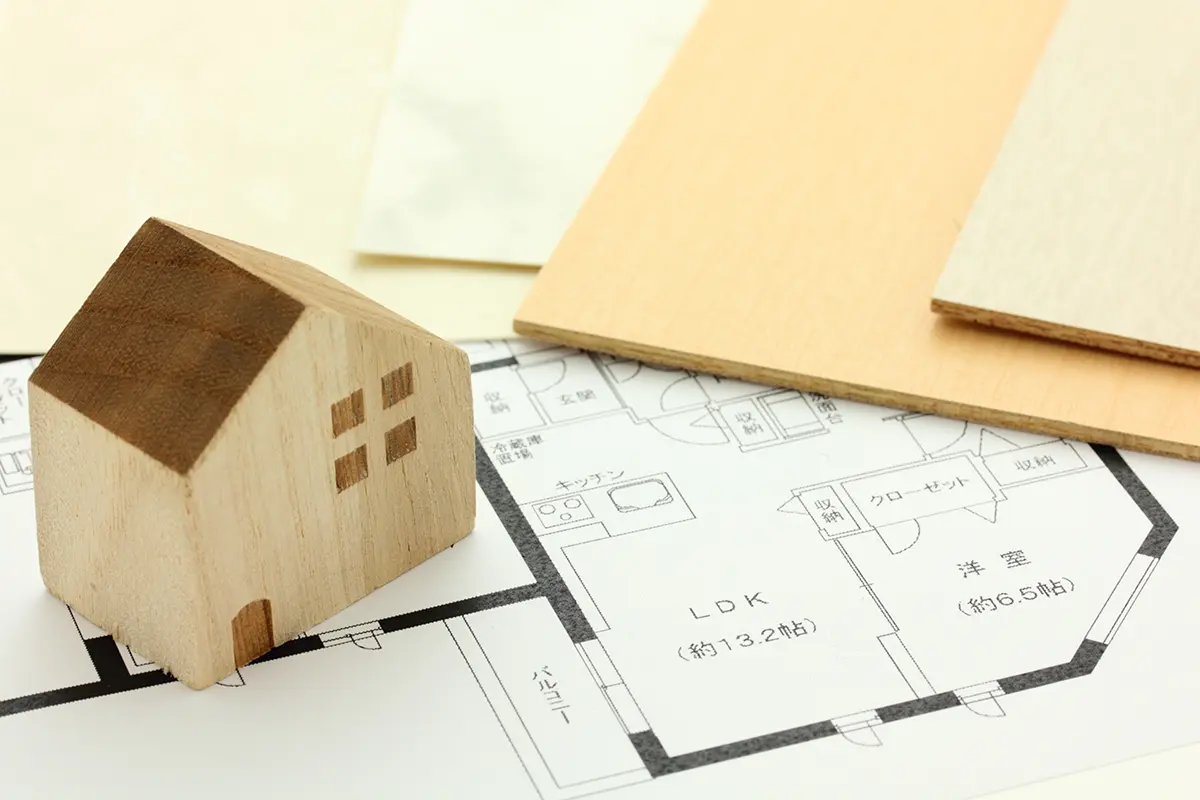2025.09.01
家づくりの際に行う地鎮祭とはどういうもの? 服装や初穂料など事前に知っておくべきこと
マイホームを建てるときは、工事の無事完了やその土地で末永く安心・安全に暮らせることを祈りたいものです。日本の神道などでは、その土地を守護してくれる「氏神様」がいるとされており、古くから人々の暮らしと安全を守ってきました。
今回は、地主神に安全を祈願する儀式である「地鎮祭」について解説します。これからマイホームの建築を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
注文住宅を建てるまでの流れについての詳細は下記の記事をご覧ください。
⇒「家を建てるまでの流れが知りたい! 年収や頭金はどれぐらい必要? 注文住宅の基礎知識」
地鎮祭ってどんな儀式?

ここでは、地鎮祭の基本的な意味や起工式との違い、宗教による対応の違いなどを分かりやすくご紹介します。
●地鎮祭とは?
地鎮祭とは、建築前にその土地の地主神を祀り、工事の無事な進行と土地・建物の末永い安全を祈願する儀式です。古くから日本に伝わる神道の行事のひとつで、「これからこの土地を使わせてもらいます」と感謝の気持ちを込めて行われます。特に住宅の新築では、家づくりのスタートを実感できるタイミングでもあり、「これからの暮らしがうまくいきますように」と願いを込めて、地鎮祭を行う方も多くいます。
日本では全国に定着している伝統的な儀式ですが、地鎮祭をやらなければいけないという決まりはありません。地域の風習にもよるので、環境や状況に合わせて判断しましょう。
●起工式とどう違う?
「地鎮祭」と似た言葉に「起工式」がありますが、意味合いが少し異なります。地鎮祭は神様に祈る宗教的な儀式であるのに対し、起工式は工事の開始を関係者に知らせるセレモニーのようなもので、企業が発注した工事や公共工事で行われることが多いです。
また、神道以外の宗教で地鎮祭のような行事を行う際も「起工式」と呼ぶ場合があります。
●キリスト教や仏教の場合は?
地鎮祭は神道に基づく儀式であるため、信仰によっては異なる方法で土地を清めることもあります。
たとえば、キリスト教徒の場合は牧師による「祝別式」を行うこともあります。仏式で行いたい場合は、土地の地主神ではなくご先祖様にお祈りをする形となります。また、無宗教の方や特定の宗教に属さない方の中には、神事自体を省略したり、簡素な形式で執り行ったりすることもあります。
地鎮祭の準備
ここでは、地鎮祭の準備について解説します。施工会社や神社が準備を手伝ってくれるケースもあるので、事前に建築主がやるべきことを相談しておきましょう。
●地鎮祭の前にやるべきこと
工事開始の1ヵ月前には施工会社と相談して地鎮祭の日時を決め、神社の予約を取りましょう。吉日とされている大安や友引、先勝の午前、先負の午後がおすすめです。
また、地鎮祭の1週間前までには参列者の人数を確定し、神社に連絡する必要があります。参列者は、建築主・工事関係者・設計者などが一般的です。親族などに同席してもらいたい場合は、遅滞なく人数を確定できるように連絡を取りましょう。
●初穂料の準備
・初穂料の相場は?
神主さんに来ていただく際には「初穂料(はつほりょう)」という謝礼をお渡しします。金額は2〜3万円が一般的ですが、地域や神社によって異なることもありますので、事前に施工会社や神社に確認しておくと安心です。
・のし袋はどこで買える?
初穂料は、のし袋に包んでお渡しします。のし袋は文房具店やスーパー、最近ではコンビニや100円ショップでも手に入ります。選ぶときは、紅白の水引がついた「蝶結び」を選びましょう。
・のし袋の書き方
のし袋の表書きには、「初穂料」もしくは「玉串料」と書くのが一般的です。どちらを使っても問題ありませんが、「初穂料」は神社向け、「玉串料」は祭壇に玉串を奉納する場合に使われることが多いです。
下段には施主(建築主)のフルネームを書きます。連名の場合は横並びで書いてもかまいません。筆ペンや毛筆で書くのが正式とされていますが、サインペンなどでも丁寧に書かれていれば問題ありません。
中包みには金額を「金参萬円」などと記載し、住所・氏名も記載しておきましょう。
●地鎮祭の費用
地鎮祭の一般的な費用は、下記のとおりです。これらは目安ですので、施工会社や神社に確認してみてください。
・初穂料(玉串料):2〜3万円程度(のし袋に入れる)
・神主の車代:1万円程度
・祭壇等の準備費(施工会社への支払い):5万円程度
・近所挨拶用の粗品代:1万円程度(1軒500〜1,000円程度)
・お供え物代:5,000円程度

地鎮祭の一般的なお供え物は以下のとおりです。お供え物は建築主が用意するケースが多いため、神社に必要なものを確認してしっかり用意しましょう。
・米:一合程度
・塩:一合程度
・水:200〜500ml程度
・酒:のし付き、一升瓶1本もしくは2本箱が主流。
・海の幸(魚):鯛、代わりにスルメなど
・海の幸(乾燥):スルメ、昆布、のりなど
・野の幸(野菜):大根、ニンジン、ナス、トマトなどから3種類
※「地面の上にできる野菜」と「地面の下にできる野菜」をそれぞれ用意する。
・山の幸(果物):バナナ、リンゴ、みかん、イチゴなどから3種類
●近隣の挨拶まわりで渡す粗品
工事中は騒音や振動が発生する可能性があるため、地鎮祭後に近隣の挨拶まわりを行うケースもあります。その際は、タオルやお菓子などの粗品を用意するのが一般的です。500〜1,000円程度で、相手が気兼ねなく受け取れるものを選ぶとよいでしょう。
●服装
地鎮祭の服装に決まりはありません。企業の建設工事ではスーツなどのフォーマルなスタイルが一般的ですが、戸建て住宅の場合は建築主がカジュアルな服装で参加するケースも増えています。もちろん神主は正装なので清潔感のある服装を意識し、身だしなみは整えましょう。
地鎮祭の流れ
次に、地鎮祭の流れについて解説します。普段はあまり参加することのない神聖な儀式なので、当日は緊張してしまうかもしれません。儀式中は神主がその都度行うべきことを教えてくれるため、安心して臨みましょう。
●大まかな流れ
地鎮祭の式典自体の時間は30分程度で、それに加えて祭壇の設置や撤去に時間がかかります。式典は「祓いの行事」「起工の行事」「供物の行事」という3つの大きな流れで進められます。地域や神社によって違いはありますが、以下のような祭儀が一般的です。
・祓いの行事
建築現場の敷地を祓い清める行事です。祭場の四方を大麻(おおぬさ)で祓い、半紙と麻でつくった切麻(きりぬさ)を撒く「四方祓(しほうはらい)の儀」を行います。

建築主と施工者が忌鎌・忌鍬・忌鋤などを持ち、草を刈ったり地を穿ったりする所作を行います。これらは、「刈初(かりぞめ)の儀」「穿初(うがちぞめ)の儀」とされ、神様に工事の開始を奉告する祭儀です。
・供物の行事
「鎮物(しずめもの)埋納の儀」として鎮物の品を捧げます。これにより神霊を鎮め、工事と生活の安全を祈念します。
・当日の注意点
当日の準備を施工会社が行ってくれる場合は地鎮祭が始まるまでに到着すれば問題ありませんが、関係者に挨拶ができるくらいの余裕を持って動くとよいでしょう。また、地鎮祭後に近隣挨拶を行う場合は、よい関係を築けるようにていねいに接することが大切です。
地鎮祭の「いまどき」事情

昔は「地鎮祭を行うのが当たり前」とされていましたが、今は事情に合わせて自由に選ぶ時代です。ここでは、そんな“いまどき”の地鎮祭事情を見ていきましょう。
●地鎮祭は義務ではない
地鎮祭はあくまでも任意の儀式であり、行うかどうかは施主の判断にゆだねられています。昔ほど「行うのが当たり前」という雰囲気はなくなってきており、「費用を抑えたい」「忙しくて準備が難しい」「宗教的に合わない」といった理由から、省略するケースも増えています。
必ず行わなければならないものではないため、家族で話し合って決めるのがよいでしょう。
●簡易なスタイルで行う地鎮祭も
最近では、地鎮祭の簡略化も進んでいます。たとえば、神主を呼ばず、施工会社と施主だけでお供え物を並べて手を合わせる簡易スタイルや、オンラインで神主が祝詞を上げるリモート地鎮祭なども登場しています。
また、初穂料やお供え物もミニマムな形式にすることで、予算を抑えつつ気持ちを込めて行えるように工夫されています。大切なのは、「土地と建築への感謝と祈りを込める気持ち」であり、形式にとらわれすぎず、無理のない形で実施することが大切です。
おわりに
地鎮祭は、家づくりのはじまりを彩る大切な行事のひとつです。必ずしも行う必要はありませんが、家族にとって記念になり、思い出として心に残ることもあります。
最近では、地鎮祭のスタイルは多様化しており、それぞれの家庭に合った形で執り行われています。事前に施工会社や神社とよく相談し、納得のいく形で準備を進めましょう。形式に縛られすぎず、土地への感謝と工事の安全を祈る気持ちを大切にして、新たな住まいへの第一歩を踏み出しましょう。
また、地鎮祭のほかにも柱や梁を組み上げたときにそれまでの工事に感謝し、その先の安全を祈願する「上棟式」や、工事完了後に今後の繁栄を祈願する「竣工式」があります。「地鎮祭」「上棟式」「竣工式」は、建築の三大祭式と呼ばれています。ぜひ下記の記事もご参照ください。
上棟式・棟上げについての詳細は下記の記事をご覧ください。
⇒「上棟式・棟上げとは何をするもの? 大工さんへのお礼としてご祝儀や手土産は必要?」
竣工式についての詳細は下記の記事をご覧ください。
⇒「竣工式とは? 住宅の完成をお祝いする場におけるマナーと服装 引き出物はどのようなものが良い?」
家づくりに関係する土用期間について下記の記事もぜひご覧ください。
⇒「土用の丑の日はいつ? 土用の期間中に家づくりで「してはいけないこと」とは」