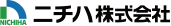2025.03.17
旗竿地とはどんな場所? 家を建てる際のメリット・デメリットと事前にチェックしたいポイント
不動産の広告などを見ていると「旗竿地」という言葉を目にすることがあります。長方形や正方形ではない「不整形地」のひとつを意味する言葉であり、しばしば扱いづらい土地として紹介されることがあります。
しかし、旗竿地ならではのメリットもあり、一概に不利な土地というわけではありません。そこで今回は、メリット・デメリットとともに旗竿地に住まいを検討するときのポイントを解説します。土地の予算を抑えたい方、希望する地域に旗竿地を見つけた方などは、ぜひご参考になさってください。
土地探しに関する詳細は、下記記事をご覧ください。
⇒「土地探しのコツを知りたい! 理想の注文住宅を目指すための探し方と注意点」
注文住宅を建てるまでの流れに関する詳細は、下記記事をご覧ください。
⇒「家を建てるまでの流れが知りたい! 年収や頭金はどれぐらい必要? 注文住宅の基礎知識」
旗竿地(はたざおち)とは
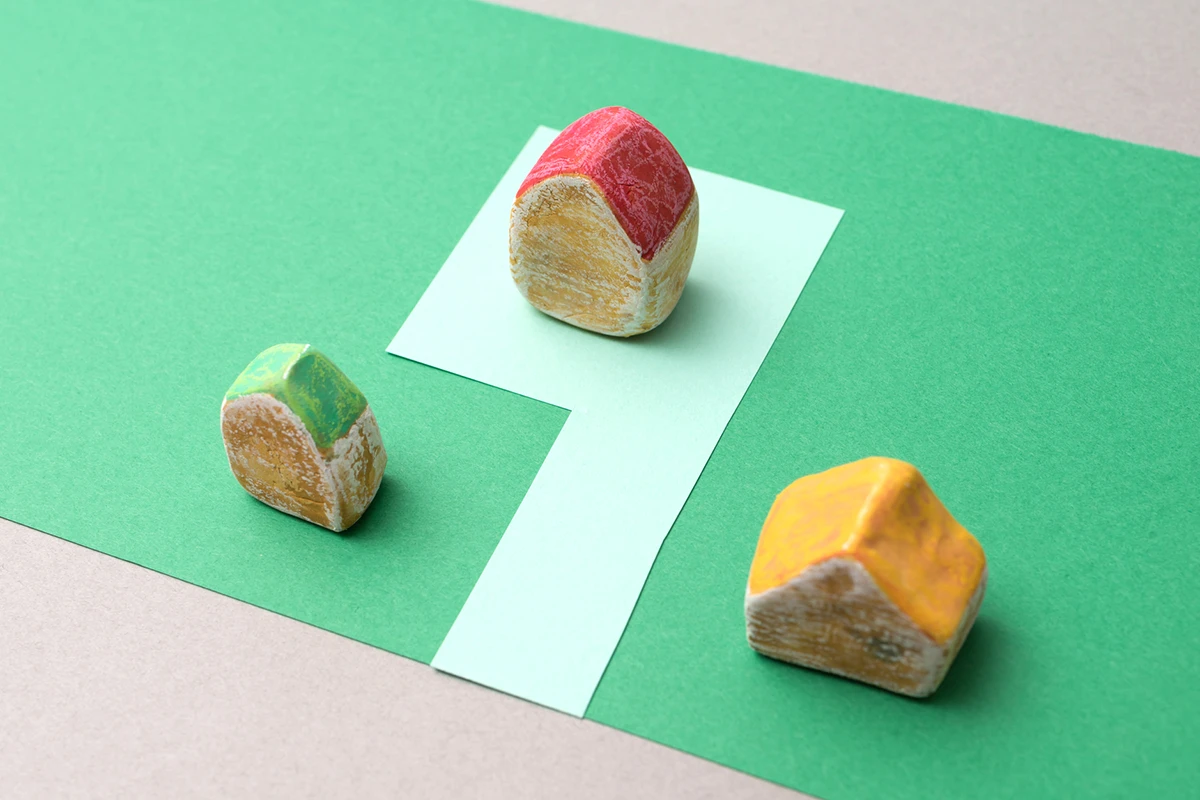
旗竿地とは、狭い路地の先に広がる敷地のことを指します。道路に面した部分から延びた路地部分が「竿」、その奥にある敷地部分が「旗」に見えるため、不動産の業界用語として使われている言葉です。正式には「路地状敷地」と呼ばれ、「敷地延長」と表現されることもあります。
都心部の古い住宅地にしばしば見られます。また、相続や売却のために奥に向かって拡がる土地を手前と奥の2つに分けて販売するために、奥側を旗竿地にするケースも多くなってきたようです。
旗竿地のメリット・デメリット

旗竿地にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょう。
●メリット
【周辺敷地の相場より低価格】
長方形や正方形をした「整形地」と呼ばれる敷地に比べ、不整形地とされる旗竿地は単位面積あたりの価格が低く設定される傾向があります。整形地に比べて2〜3割程度安いことが多いため、土地の価格を抑え、建物にコストを掛けたい施主にとってはメリットのある土地といえます。
【建物の面積を大きくすることができる】
建築基準法では、建築物に対して建ぺい率や容積率を定めています。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合、容積率とは、敷地面積に対する延床面積の割合であり、敷地の広さに応じて建築物の面積が制限されてしまうのです。
建ぺい率・容積率を算出する基準となる敷地面積ですが、旗竿地では路地(竿)部分の面積を敷地面積に含めることができます。広い家を建てるには建ぺい率・容積率をクリアするために広い敷地が必要ですが、不整形地ゆえに広い敷地を低価格で手に入れられることはメリットといえるでしょう。
【路地を駐車場などに活用できる】
基本的には道路までの避難通路として空けておくべきである路地部分ですが、スムーズに避難できる通路幅を確保したうえで駐車場や物置として活用しているケースがあります。ただし、一般的に駐車スペースにするには2.5〜2.7mの幅が必要になりますし、使い方によっては隣地の日当たり環境を悪化させるなどのトラブルに繋がることもあります。安全・生活面における専門家の助言を仰ぐようにしましょう。
【静かな環境で暮らせる】
旗竿地は路地部分の長さの分だけ道路から離れています。そのため、車の走行音や通行人の話し声が気にならない静かな環境で暮らせるという特徴があります。後述のとおり日当たりなどのデメリットはありますが、落ち着いた環境で静かに暮らしたい方にとっては魅力的な敷地かもしれませんね。
●デメリット
【風通しや日当たりを確保しにくい】
旗竿地は奥まった位置にあるため、風通しや日当たりを確保しにくい傾向があります。この問題をいかに解決するかで家の快適性が変わるため、あらかじめ周囲の環境を確認し、設計者とよく相談して計画を進めるようにしましょう。
具体的には、以下のような対策が考えられます。
・1階に寝室や浴室、日当たりの良い2階に居間を設け、団らんスペースに光・風を取り入れやすくする
・隣家と近接している都市部ではプライバシー確保の目的も合わせて、採光部の幅を狭くしつつ、上に延ばす
・吹き抜けや天窓・高窓を設け、家の中へ光を取り込みやすくする
・中庭や光庭を設置し、家の中に光・風を通す
・建物を北側に寄せ、南側に日差しを取り入れるスペースを確保する
【路地の外構工事が必要】
旗竿地は家の周りだけでなく路地部分にも外構工事が必要になるケースがあります。具体的には以下のような外構が考えられます。
・路地を歩いているときのプライバシーを守る目隠しとなるフェンス
・路地を安全に歩くための照明
・家から道路までを繋ぐ給排水管
旗竿地で家づくりを検討するときは、外構工事の費用も念頭に置いておくようにしましょう。
【土地評価が低くなりがち】
旗竿地の価格が低いことをメリットとして紹介しましたが、それと引き換えに整形地と比べると土地評価は低くなるのが一般的です。銀行で住宅ローンを組む場合は、土地の担保評価が低くなり多めの自己資金が必要になる可能性があります。
旗竿地を有効に活用するためのポイント

●自治体の旗竿地のルールを確認する
建築基準法では、「建築物を建てる土地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と定められています。これは国が法律で定める最低基準であり、自治体によってはさらに厳しい基準を設けています。東京都の場合は以下のとおりです。
・路地状部分の長さが20m以下の場合、路地状部分の幅員は2m以上とする
・路地状部分の長さが20mを超える場合、路地状部分の幅員は3m以上とする
・路地状部分の幅員が4m未満の場合、一部を除く階数が3以上の建築物を建築してはならない
制限によっては理想の家を計画するのが難しいケースもあるので、旗竿地を検討する場合は自治体のルールを事前にチェックしておきましょう。
●路地部分を有効活用する方法を考える
旗竿地で住まいを検討する際は、路地部分を効果的に活用できるかが暮らしを大きく左右します。駐車場や物置として有効活用できれば、それだけ家を建てられる実質的な敷地が広くなり、幅広い暮らし方が可能になります。将来的に必要になる車の台数などを具体的にイメージし、無駄なく敷地を使うように意識してみてください。
●中庭・光庭・吹き抜けなどの工夫で日当たりや風通しを確保する
デメリットの部分でも紹介しましたが、旗竿地の課題は「いかに日当たりと風通しを確保するか」です。空調などの建築設備で住環境を改善するのも有効な方法ですが、中庭・光庭・吹き抜けといった建築的な工夫で快適かつエコな生活に近づけることもできます。設計者と相談しながら理想の暮らしを目指しましょう。
おわりに
旗竿地には不整形地特有のデメリットがありますが、敷地・立地の環境・特性を読み解くことで対策できるケースが数多くあります。土地が相場の2〜3割安く手に入るという大きなメリットがあるため、建物にコストを掛けて理想の家に近づけることもできるでしょう。旗竿地だからといって敬遠せず、「こう使えばデメリットを気にせず理想の暮らしができそう」という考え方でイメージを膨らませてみてはいかがでしょうか。