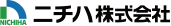2025.04.11
住宅性能評価書とは? 評価を受けるメリットと住宅性能表示制度での評価項目ご紹介
住宅を建てる過程で、住宅ローンを組んだり、助成金や税制優遇を申請する時に「住宅性能評価書」という書類の提出を求められることがあります。また、物件を売却する際にも、この書類があると評価額のアップにつながるといわれています。
「住宅性能評価書」とはどんな書類なのか、どういうタイミングで誰が作成するのか、詳しく解説していきます。
注文住宅を建てるまでの流れに関する詳細は、下記記事をご覧ください。
⇒「家を建てるまでの流れが知りたい! 年収や頭金はどれぐらい必要? 注文住宅の基礎知識」
住宅性能評価書とは
ここではまず、住宅性能評価書の概要について解説します。
●「住宅性能表示制度」に基づく評価
住宅性能評価書とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、住宅の性能を評価する制度です。評価基準は国によって定められ、それに基づいて第三者機関が評価を行います。住宅の品質や安全性、快適性、環境性能など、さまざまな側面において一定の基準を満たしていることを証明するものです。
●住宅性能評価書は2種類
住宅性能評価書は、建築の進行度合いによって2つに分かれます。
・設計住宅性能評価書
設計段階で、住宅がどのように作られるか、設計図面や仕様書をもとに評価が行われます。この段階では、住宅性能表示制度を基に、設計がどのように性能基準を満たしているか、またはどの基準をクリアしようとしているかが評価されます。書類の中には住宅の耐震性や省エネルギー性など10分野にわたる評価が記載されます。
住宅ローンの申請や長期優良住宅の認定のために提出するのは通常こちらの評価書です。
・建設住宅性能評価書
住宅が完成した段階で、最終的な住宅性能評価書が発行されます。完成した住宅が設計通りに性能基準を満たしているかどうかを最終的に確認するものです。住宅が引き渡される前に第三者機関によって行われ、耐震性、省エネルギー性能、劣化対策などの評価が最終的に決定されます。
これらの評価が終わった後、住宅性能評価書が正式に交付され、施主に渡されることになります。
また、住宅の建設が進む中で、中間評価を行うこともあります。建築が計画通りに進んでいるか、性能面での基準が守られているかを確認するためのものです。例えば、構造材の使用や断熱材の施工状況など、実際の施工が設計通りになっているかをチェックします。
評価を取得することで住宅の品質や安全性を客観的に証明できるほか、住宅ローンの金利優遇や保険の割引などが受けられる場合もあります。
参考:国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度 住宅性能表示制度ガイド」
●長期優良住宅との違いは?
一方で住宅の評価基準には「長期優良住宅」というものもあります。これは長期間にわたり使用する住宅の耐久性や維持管理の容易さ、省エネルギー性などを国や地方自治体が評価・認定するものです。長期優良住宅の認定を受けるとことが必須の税制優遇や補助金制度もあります。
住宅性能評価書は住宅の性能を評価・表示するものであり、第三者機関が認定を行います。ただし2022年からは、住宅性能評価と長期使用構造等の一体申請が可能になりました。
それまでは「指定確認検査機関」「民間評価機関」といった第三者機関に認定を受けるのと並行して、別に書類を用意して自治体に「長期優良住宅」であることを認定してもらう必要がありました。現在は住宅性能評価書に長期優良住宅の基準を満たしていることも記載され、その評価書をもとに自治体や国の機関が判断することになっています。書類を二重に作る必要もなく、審査のスピードも上がりました。
参考:国土交通省「品確法第6条の2」
住宅性能評価書のメリット

住宅性能評価書を取得することでどんなメリットがあるのでしょうか。
●住宅の性能が保証されるため安心
住宅性能評価書は、第三者機関によって住宅の性能が客観的に評価される証明書です。これにより耐震性や省エネルギー性など、住宅の安全性や性能が担保されます。
第三者による評価なので施工ミスや不具合のリスクが低減し、購入者や居住者にとって信頼性が向上します。評価を受けることで品質に対する安心感が得られ、万が一のトラブル時にも確かな基準が基づいた対応が可能です。
●住宅ローン・地震保険等で有利になる
住宅性能評価書を取得した住宅は、住宅ローンや地震保険の契約時に有利な条件を受けられる場合があります。
これは長期的なコスト削減につながります。ただし実際の金利は金融商品によって異なるため、契約前に確認しましょう。
●税制上のメリットが大きい
住宅性能評価書を取得している住宅を贈与する場合、贈与税の非課税枠が増加します。具体的には一般住宅の非課税枠が500万円に対して、「質の高い住宅」は1000万円となります。ただしこの制度は2026(令和8)年が適用期限とされています。実際に利用する際には、国土交通省のサイト等をご確認ください。
また長期優良住宅の認定を受けた評価書があれば、自治体によって固定資産税の減額、住宅ローン減税、登録免許税の軽減などさまざまなメリットがあります。
参考:国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」
●資産価値向上につながる
第三者機関による性能評価は、将来の売却時に有利に働く場合があります。とくに耐震性や省エネルギー性能が高い住宅は魅力的な条件で、取引価格を維持しやすくなります。
●トラブルの発生時に紛争処理機関を利用できる
住宅性能評価書を取得した住宅は、万が一のトラブル時に紛争処理機関を利用できます。評価基準に基づいて住宅の性能や施工状況を調査し、第三者の立場で解決策を提案してくれるのがメリットです。
これによりトラブルが発生した場合にでも公正かつ迅速に問題を解決できるため、大きな安心材料となります。
住宅性能は10分野32項目にわたって評価される

住宅性能は、新築の場合、10分野32項目にわたって評価され、住宅性能評価書に記載されます。
①構造の安定に関すること(耐震・耐風・耐積雪等級について)
地震や風、雪などの自然災害に対する住宅の耐久性を示します。耐震等級、耐風等級、耐積雪等級に加え、地盤や基礎の構造についても評価されます。
②火災時の安全に関すること(耐火等級・延焼防止性能について)
耐火等級や延焼防止性能に関する評価です。耐火等級、延焼を防止するための対策等を評価します。
③劣化の軽減に関すること(劣化対策等級)
住宅が時間とともに受ける劣化や腐食に対する対策を評価します。耐久性を高めるために使用される建材や工法が基準を満たしているかを確認し、長期間にわたって品質を保つための設計が施されているかに対する評価です。
④維持管理・更新への配慮に関すること(維持管理等級について)
住宅の維持・管理が容易であるかどうかを示します。設備の点検や交換が簡単に行える設計や、清掃のしやすさなど、住宅が長期的に快適に維持できる工夫が評価されるのが特徴です。適切な維持管理により住宅の劣化を防ぎ、居住者の負担を軽減します。
⑤温熱環境に関すること(断熱性能等級・一次エネルギー消費量等級について)
省エネ法の「住宅の省エネルギー基準」の水準に準拠した評価基準です。暖房・冷房にかかるエネルギー使用量を抑える設計がなされているか確認できます。
⑥空気環境に関すること(ホルムアルデヒド対策・換気設備について)
ホルムアルデヒド対策や換気設備に関する項目です。ホルムアルデヒドは有害物質で、これを防ぐための建材が評価されます。また換気設備が適切に設置されているかも確認します。
⑦光・視環境に関すること(採光性能・照明環境について)
光・視環境の評価は、採光性能と照明環境に関する項目です。自然光が十分に取り入れられるかを確認します。
⑧音環境に関すること
外部からの騒音対策、内部の遮音性、床の衝撃音対策についての評価です。外部の騒音(自動車や電車などの走行音)を遮る設計、部屋間の音漏れを防ぐための壁や床の工夫、マンションなどで特に重要な床の衝撃音対策を評価します。
⑨高齢者等への配慮に関すること
高齢者等に配慮したバリアフリー設計への評価です。段差の有無、手すりの設置、通路の広さなどが基準を満たしているかを確認し、生活しやすい環境を提供します。
⑩防犯に関すること
「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載・公表されていることを表す「CPマーク(Crime Preventionマーク)」付き建材を使用しているかを評価します。
住宅性能評価書の取得方法

●事前打ち合わせ
住宅性能表示書の取得には、設計者(建築士)や施工会社との事前打ち合わせが大切です。どのような性能評価を受けるべきか、どの基準を満たすためにどう設計を進めるべきかを一緒に考えてもらいましょう。また施工段階での確認や施工方法に関する質問は施工会社に相談しますが、設計者を通した方がスムーズな場合があります。
●評価申込み
評価を受けるために評価機関(指定住宅性能評価機関)に申し込む必要があります。申込み時には、必要な書類や設計図面、詳細な仕様書などを提出する必要があります。
●設計段階での評価
住宅の設計段階で、設計図に基づいて性能評価を受けます。この段階で、住宅がどのような性能を持っているのか(耐震性、耐火性、省エネルギー性能など)をチェックします。提出された設計図書類や必要な資料を基に、第三者機関が住宅の性能を審査します。評価機関は、住宅が性能基準を満たしているかを検査し、評価します。
●設計住宅性能評価書の交付
設計段階で評価機関に申し込み、住宅が各性能項目(耐震性、省エネルギー性、耐火性など)についてどのように評価されるかを示した書類です。この評価書は、設計段階で住宅が性能基準に適合していることを証明します。ローン審査のため金融機関や保険会社などに提示できます。
●建設住宅性能評価書の交付
住宅が完成した後に、最終的に住宅が設計通りに建てられ、全ての性能基準が満たされているか評価されます。施工後の評価が完了すると、建設住宅性能評価書が交付されます。評価書には住宅が基準を満たしているか、どの性能等級に該当するかなどの詳細が記載されています。一般的にはこの評価書を取得した後に引き渡しが行われます。
住宅性能評価書のよくある疑問

ここでは住宅性能評価書のよくある疑問をまとめて紹介します。
●住宅性能評価書の取得は義務?
住宅性能評価書の取得は義務ではなく、任意で行うものです。新築住宅を建設する際に評価書を取得するかどうかは、個人の判断で決められます。
しかし評価書を取得することで住宅の品質や安全性が客観的に証明されるので、取得した方が多くのメリットを享受できるでしょう。
●取得費用の目安
住宅性能評価書の取得費用は、一般的に10〜30万円程度が目安です。費用には、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書のそれぞれにかかる料金が含まれます。
ただしこの金額は、評価を依頼する機関や住宅の規模・構造によって異なります。詳細な料金については、評価機関の最新の資料を確認することが重要です。
参考:日本確認検査センター「新築住宅 性能評価料金」
●あとから取得できる?紛失した場合、再発行は可能?
新築住宅の場合、住宅性能評価書は後から取得することはできません。評価書は建設前の段階から評価されており、設計段階から基準を満たしている必要があるからです。
ただし評価書を紛失した場合は、再発行が可能です。再発行は評価機関に申請し、所定の手続きを実施しましょう。
まとめ
住宅性能評価書は住まいの性能を客観的に評価した書類です。住宅ローンの金利優遇や紛争処理などが受けられるので、取得をおすすめします。第三者の評価を得ることで、納得のいく住まいづくりが実現できることでしょう。
断熱改修について下記の記事もぜひご覧ください。
⇒「住宅省エネ補助金は使える? 外壁張り替えリフォームと断熱改修を解説」