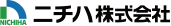2025.11.07
三隣亡とは? 地鎮祭など建築関連の行事には不向きな日? 意味や由来、やってはいけないことは?
三隣亡という言葉を今までに聞いたことはありますか? 実は建築に関することをしてはいけないと言い伝えられている日で、地鎮祭などを避ける習わしがあります。
本記事ではその意味や由来、さらには建築に関係する暦の種類(選日・十二直・六曜)も詳しく解説しています。新築やリフォームをする際の参考として、ぜひチェックしてみてください。
注文住宅を建てるまでの流れに関する詳細は、下記記事をご覧ください。
⇒「家を建てるまでの流れが知りたい! 年収や頭金はどれぐらい必要? 注文住宅の基礎知識」
地鎮祭についての詳細は、下記記事をご覧ください。
⇒「家づくりの際に行う地鎮祭とはどういうもの? 服装や初穂料など事前に知っておくべきこと」
三隣亡(さんりんぼう)とはどんな日?

ここではまず、三隣亡の概要について解説します。
●三隣亡の意味・由来
「三隣亡(さんりんぼう)」は「この日に建築関係の工事をすると、向こう三軒両隣まで滅ぼす」とされている建築の大凶日です。地鎮祭や上棟式など、建築にまつわる行事を避けるべき日として知られています。江戸時代には漢字で「三輪宝」と書く吉日でしたが、誤って「三隣亡」と記されたことが由来という説が有力です。
現在でも山形県など一部の地域では、施工日を決める際の参考にしているケースがあります。ただし、あくまで民間信仰に基づくもので、科学的な根拠はありません。
●三隣亡のカレンダー該当日
三隣亡の日は暦によって決まっており、各月の特定の干支の日が該当します。1・4・7・10月は「亥の日」、2・5・8・11月は「寅の日」、そして3・6・9・12月は「午の日」が三隣亡です。
年によって多少のずれはありますが、月に2〜4日程度が当てはまります。
●三隣亡におすすめしないこと
「三隣亡の日に建築関連の行事をすると、火事や災いを招いて三軒両隣まで不幸が及ぶ」とされています。そのため、地鎮祭や上棟式、リフォーム工事の着工といった建築関係の行事は避けることが多いようです。
また、引越しや納車、家や家具などの大きな買い物、さらには結婚式などの祝い事も控えた方がよいとする場合もあります。ただし、上記で述べたように、これらは民間信仰によるもので、実際に悪いことが起きるという科学的根拠はありません。必要以上に気にし過ぎることなく、参考程度にするのがおすすめです。
建築に関する暦の種類①選日

ここでは、建築に関する暦の種類である「選日」について解説します。これは日の吉凶を占う暦の一種で、三隣亡も含まれています。選日の中から、建築や引越し等に関する項目をピックアップしてまとめてみました。
●三隣亡(さんりんぼう)
三隣亡は建築関係においては特に注意すべき大凶日とされ、「この日に建築を始めると三軒両隣まで滅ぼす」といわれている日です。地鎮祭や上棟式、改築などは避けるのがよいとされています。地域によっては現在でも重要視されており、建築の際は参考にされることがあります。
●八専(はっせん)
八専とは、六十干支の「壬子(みずのえね)の日(49番目)〜癸亥(みずのとい)の日(60番目)」までの期間から間日(まび)を除外した8日間を指します。元は軍事上の忌日でしたが、転じて地鎮祭や上棟式で柱を立てることも避けるべき不吉な日とされるようになりました。
ちなみに間日は「癸丑(みずのとうし)、丙辰(ひのえたつ)、戊午(つちのえうま)、壬戌(みずのえいぬ)」の4日間で、凶が和らぐことから工事や移転も問題ないと考えられています。
●天一天上(てんいちてんじょう)
天一天上とは方位神である「天一神」が天上に昇る期間で、癸巳(みずのとみ)〜戊申(つちのえさる)までの16日間を指します。この期間は方角の忌みがなく、どの方角へ行っても災いが起きないとされる吉日です。
そのため、建築や引越しなどの方位を気にする行事に適した時期とされています。
●一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
一粒万倍日は、「一粒の籾が万倍にも実る」という意味を持つ大吉日です。努力や始まりが大きく実を結ぶ日とされ、仕事始め、開業、契約、財布の新調などに適しています。
建築では地鎮祭や上棟式など、新しいことを始めるための行事におすすめです。ただし、借金や争いごとを始めると「悪いことも万倍になる」とされるため、注意が必要な日でもあります。
●不成就日(ふじょうじゅび)
不成就日は、その名の通り「何事も成就しない日」といわれている凶日です。8日ごとに割り当てられており、1ヶ月に4日程度が不成就日となります。
建築着工、引越し、結婚、開業など、「始まり」を意味する行為には不向きとされます。新しいことを始めたり、契約を結んだりするのは避けましょう。
●大犯土・小犯土(おおづち・こづち)
大犯土・小犯土は、土を動かす作業を忌む期間です。大犯土は庚午(かのえうま)〜丙子(ひのえね)までの7日間、小犯土は戊寅(つちのえとら)〜甲申(きのえさる)までの7日間です。「土を犯す」とされる工事や掘削、地鎮祭などは避けるのがよいとされています。
建築に関わりのある暦の種類②十二直

ここでは、建築に関する暦の種類である「十二直(じゅうにちょく)」について解説します。現在ではあまり使われていませんが、建築や引越しの吉凶を見るために用いられることがあります。
●建(たつ)
「建」は物事の始まりを意味する日で、新築や開業、契約ごとなど、新しいことを始めるのに適した吉日です。地鎮祭や上棟式の建築に関連する行事にもよいとされます。
●除(のぞく)
「除」は悪いものを取り除くという意味を持ち、掃除や修繕、病気治療、厄払いなどに適した日です。一方、新しいことを始めるのには向かず、建築の着工や引越しなどは避けるのが無難です。
●満(みつ)
「満」は物事が満ちる日とされ、結婚、引越し、開業などの祝い事に適した吉日です。幸福や成果が満ちるという意味を持つため、建築では完成式や引き渡しなどの行事にもよいとされています。
●平(たいら)
「平」は平穏や安定を表し、万事において吉とされる日です。建築の着工や引越し、結婚、契約など、あらゆる行事に向いています。
●定(さだん)
「定」は物事を定めるのに良い日で、契約、開業、結婚など「決定」を伴う行為に適しています。建築では設計の確定や契約締結、引渡しなどに吉とされます。ただし、植栽の植え替え、訴訟等には不向きです。
●執(とる)
「執」は執り行う・着手する日で、建築の着工や契約など、行動を起こすのによい日です。仕事始めやプロジェクトの開始に適している一方、争いごとや交渉には不向きとされています。
●破(やぶる)
「破」は破れる・壊れることを意味し、建築や婚礼などの祝い事には不向きです。そのため、着工や引越し、契約などは避けるのが無難です。しかし、一方では訴訟や離別の日取りに選ばれることがあります。
●危(あやぶ)
「危」は不安定や危険を意味する日で、建築や旅行など、事故のリスクがある行為は避けた方が良いとされます。ただし、神事などには向いているといわれています。
●成(なる)
「成」は物事が成就する日で、建築、契約、開業、婚礼など、成功を願う行事に適した吉日です。努力が実を結ぶ日といわれていて、建築関連では上棟式や引渡しにもよい日とされています。
●納・収(おさん)
「納」は収める・完了させる日を指し、収納や引越し、支払い、引渡しなどに向いています。建築工事の完了や入居、引渡しのような“締めくくり”に適した吉日です。
●開(ひらく)
「開」は門出や新しい始まりを意味しており、開業、移転、引越し、結婚などの祝い事に最適な吉日です。運気を開く明るい日とされ、建築関連でも地鎮祭や新築祝いなどに向いています。
●閉(とづ)
「閉」が表すのは物事を終える・閉じる日なので、契約や移転、建築の着工など、新しいことを始めるには不向きです。ただし、建物の取り壊しや解体、仕事納め等には問題ないとされています。
建築に関わりのある暦の種類③六曜

ここでは、「六曜(ろくよう)」について解説します。この暦は建築に限らず、広く活用されています。
●先勝(せんしょう、さきかち)
「先勝」は「先んずれば勝つ」という意味を持ち、午前中が吉、午後が凶とされる日です。急ぎの用事や契約、着工などは午前中に行うのがよいとされています。建築関係でも縁起を担いで地鎮祭や上棟式を午前に行うことがあります。
●友引(ともびき、ゆういん)
「友引」は「友を引く」という意味から、祝い事には吉日とされますが、葬儀を行う際は避けられる日です。建築や引越しでは「良い縁を引く」として好まれ、契約や地鎮祭にも選ばれることが多い日です。
●先負(せんぷ、さきまけ)
「先負」は「先んずれば負ける」という意味を持ち、午前中が凶、午後が吉とされます。焦らず穏やかに行動するのがよいとされる日で、建築の打ち合わせや契約、儀式等は午後に行うのがよいといわれています。
●仏滅(ぶつめつ)
「仏滅」は六曜の中でも最も良くないとされる日で、「すべてが滅する」という意味を持っています。そのため、結婚式や地鎮祭などの祝い事には不向きです。
●大安(たいあん)
「大安」は「大いに安し」と書く通り、六曜の中で最大の吉日です。万事において吉とされ、建築の着工、地鎮祭、上棟式、引渡し、引越しなど、すべての行事に向いています。
●赤口(しゃっく、しゃっこう)
「赤口」は「火や刃物に注意すべき日」とされ、午前11時から午後1時ごろ(正午前後)のみが吉、その他の時間帯は凶といわれています。火事や事故に注意すべき日なので建築や工事には不向きです。
三隣亡でよくある疑問

ここでは、三隣亡に関してよくある疑問をご紹介します。新築やリフォームを検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
●建築関連の行事は絶対に避けるべき?
三隣亡は「建築に不向き」とされる日ですが、あくまでも占いの一種で科学的な根拠はありません。そのため、地鎮祭や上棟式等の日程調整が難しければ、気にしすぎる必要はないでしょう。
家づくりに関係する土用期間について下記の記事もぜひご覧ください。
⇒「土用の丑の日はいつ? 土用の期間中に家づくりで「してはいけないこと」とは」
現代では「気持ちの問題」として参考程度にとらえる人が多く、日取りより天候や参加者の都合を優先するケースも増えています。
●建築関連におすすめの日取りは?
建築に関しては、十二直の中でも「建(たつ)」「満(みつ)」「平(たいら)」「定(さだん)」「成(なる)」「開(ひらく)」の6つが“建築吉日”といわれています。
これらの日は物事の始まりや安定、完成などを象徴しているため、地鎮祭・着工・上棟式・引渡しなどに適しています。縁起の良いスタートを切りたい場合には、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
三隣亡は「建築を行うと三軒両隣まで災いが及ぶ」とされる建築の大凶日で、地鎮祭や上棟式などを避けるべきとされていますが、あくまでも科学的根拠は無いので気にしすぎないようにしましょう。
もし、暦を重視するなら節目の行事には十二直の「建・満・平・定・成・開」といった“建築吉日”を選ぶのがおすすめです。ただし、暦の吉凶にとらわれすぎず、天候などの現実的な条件を踏まえ、安心できる日取りを決めるようにしましょう。